初めてのオンデマンドスクーリングを終えて
2025.04.01
魚崎 祐子
2024年12月〜2025年2月にかけて、通信教育課程では初めての試みとなるオンデマンドスクーリングを行いました。まだ受講した人が少なく、イメージのわかない方々もおられるかと思いますので、今回行った授業の流れや特徴などについて紹介したいと思います。
このスクーリングはオンデマンド教材を用いて、個々のペースを重視しながら学修していくスタイルです。これまで開講されてきたブレンディッドスクーリングにおいても前半のメディア授業はオンデマンド教材を用いていたので、それらの動画の分量や内容を目安として作成し、配付資料やテキストとともに学修を進めてもらうこととしました。ブレンディッドスクーリングとの違いは15回の授業全てにおいてオンデマンド教材を用いるため、直接顔を合わせることがないまま、授業が進んでいくという点です。教員は各学修者がどの回まで試聴を終えているか、課題の取り組み具合はどうかなどといったことを把握できるものの、何を考えどのように取り組んでいるのかということが見えづらくなります。またどうしても受身の学修になってしまいやすいので、動画を流しているだけ、なんとなく試聴しているだけ、という学修にならないようにということを意識しました。そこで、動画では直接話していないことも含め、動画の内容をもとにして各学修者が考える必要のある課題をワークシートとして設定し、ワークシートに書かれた内容から学修者の考えたことを探るようにしました。白黒はっきりつく課題ではないものも多かったので、それなりに学修にかける時間を必要とした人も多かったように見受けられましたが、各学修者が「考える」ことができていたように思います。
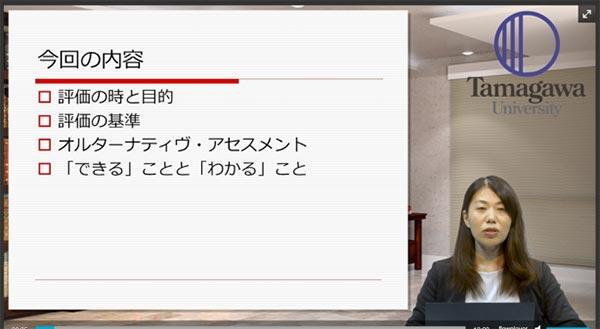

オンデマンドスクーリングの持つ大きなメリットは、期間内であれば「いつでも」「どこでも」学修できるということです。特に通信教育課程の学生は仕事や家事、育児や介護など様々なものを抱えている方々が多いと思われますので、自分の都合に合わせて学修を進められることが好都合であることも多いでしょう。しかし一方、多くの人にとって「いつでも」「どこでも」というのが口で言うほど容易ではないということも知っています。私自身も経験がありますが、他のことが忙しいとどうしても「いつでも」「どこでも」できることは後回しになってしまうものです。そこで学修に向かわせる仕組みを作る必要があると考え、今回は各動画の視聴や各課題の提出期間についてやや細かめに定めました。とはいえ厳密な縛りではありませんので、決められた期間の中で各自が調整することが可能です。毎週同じペースで学修する必要はなく、個々のスケジュールに合わせて、余裕のある時期には多めに受講するといった対応をしていた人もおられました。また指定の期間を過ぎた後も含め、何度でも見直すことができるので、他の回の学修をした後に気になった点をまた確認するといったこともできます。
一方で学修を進めるペースが人によって違うということにより、ディスカッションで意見を出し合うといった場面ではタイムラグが生じてしまうという難しさがあります。このことはあらかじめ予想されていたことですので、今回のスクーリングではディスカッションの設定は少なめとし、それぞれから出され意見や事例などを教員がまとめて後日クラス全体に共有するという方法を取りました。このことにより、自分とは異なる考えに触れたり、自分と同じように頑張っている人がいるのだという励みにつながったりするという一定の効果があったように見受けられましたが、その場で考えを作り上げていくという形にはなりづらいという限界もありました。
以上のようにオンデマンドスクーリングは、直接的な対話をより重視したいという人の要望にはあまり合っていないかもしれません。一方で自分のスケジュールやペースを重視し、取り組み方の軽重も自分で調整したいという人には向いていると思います。通信教育課程では他にも対面、ブレンディッド、オンラインといったスクーリングの形態があり、それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の好みや都合にあわせて選択できると良いでしょう。
今年度も新たな科目においてオンデマンドスクーリングが開講される予定です。授業の進め方は科目や担当教員によって異なる点もありますので上記の流れは1つの例にすぎませんが、自分のペースで進めていくこのスクーリングが自分に合っているかもしれないと思った皆さんの選択肢の1つになることを願っています。
プロフィール

- 教育学部教育学科 通信教育課程 教授
- 早稲田大学大学院人間科学研究科 博士後期課程修了
博士(人間科学) - 専門は学習心理学、教育心理学
- 早稲田大学助手などを経て現職。
- 著書に『Dünyada Mentorluk Uygulamaları』(共著、Pegem Akademi Yayıncılık、2012年)、『テキスト読解場面における下線ひき行動に関する研究』(単著、風間書房、2016年)、『研究と実践をつなぐ教育研究』(共著、株式会社ERP、2017年)、主要論文に『配布資料の有無が授業中のノートテイキングおよび講義内容の説明に与える影響』(単著、日本教育工学会論文誌(39)、2016年)、『短期大学生のノートテイキングと講義内容の再生との関係−教育心理学の一講義を対象として−』(単著、日本教育工学会論文誌(38)、2014年)などがある。
- 学会活動:日本教育工学会、日本教育心理学会、日本教授学習心理学会、日本発達心理学会、日本教師学学会 会員




