科学するTAMAGAWA 多文化共生の世の中に
社会の多様化、グローバル化が進み、
多文化共生をめざした異文化理解はますます重要性を増しています。
言葉や知識の習得も大切ですが、
自分の中にある偏見に気づくことが必要です。
異文化理解とは何か

近年のグローバル化の進展により、多様な人々との共生や協働がますます重要視されています。それにともない、外国語や外国文化を学ぶ機会も増えていますが、それで本当に異文化理解が深まるものでしょうか。そもそも、異文化理解とはどういうことを意味するのでしょうか。
「異文化理解とは、自分の中の“あたりまえ”を打ち破ることです」。そう話すのは、教育学部で異文化間教育、国際理解教育を研究している大谷千恵准教授。全学部生が共通で学ぶユニバーシティ・スタンダード科目の「異文化理解と教育」を担当しています。今回は大谷准教授のお話から、異文化理解とは何かについて掘り下げます。
自分の中にある偏見への気づき
 『異文化理解と教育』授業風景
『異文化理解と教育』授業風景『異文化理解と教育』という科目は全学部生が履修できますが、その多くは教員をめざしている学生だそうです。「グローバル化が進む現在の教育現場では、外国にルーツを持つ児童・生徒や帰国児童・生徒など、多様な児童・生徒の指導や支援ができる教員が求められています。したがって、教員をめざす学生が多文化共生や異文化理解について学ぶことはとても大切です」と話します。「しかし、単に『○○ではこういうことが行われている』とか『○○ではこう考えられている』という知識だけでは、本当の理解には到達できません。外国の文化や習慣を知ることは大切ですが、異なる視点から自分の中にある偏った常識や偏見に気づくことが必要なのです。それが、自分の中の“あたりまえ”を打ち破るという意味です」。
特に日本の学校教育の現場は、ひとつの方向に向かわせる力が強く働いている、と指摘します。「たとえば、クラス目標などに『みんな仲良く』といった標語が掲げられている教室をよく目にします。もちろん、みんなが仲良くするのは大切なことですが、だれとでも親友になれるわけではないですよね。中には独りでいたい子もいるでしょう。そういう子をむりやり輪の中に引っ張り込むことは仲良くすることとは違います。お互いに不快にならない距離を見つけて接っしていくことが、『みんな仲良く』の意味するところでしょうが、言葉が抽象的すぎて子どもたちにその意味がきちんと伝わっていない場面を目にします。もう1つ、朝礼など男女で分かれて整列したり、出欠確認は出席番号順に男子から呼ばれる場面も見られます。このような日常のよくある光景や習慣からも児童・生徒は埋め込まれた価値観を無意識に学んでいます」。

こうした積み重ねが、子どもたちに偏った価値観や偏見を植え付けると大谷准教授。教える教員側の偏見についても指摘します。「留学先のサンディエゴで観察していた小学校では、宿題を忘れた子どもに対して、担任は『いつもこうだ』『やる気がない』と決めがちでした。しかし、子どもの話をよく聞くと、前日に兄がギャングの抗争に巻き込まれて銃で撃たれたとか、宿題をやろうにも家に鉛筆も机もない家庭だったなど、いずれも支援を必要としている子供たちでした。『宿題をしなかった』と『宿題をできなかった』では、大きな違いです。日本でもアメリカでも、教員になる人の多くが、教育的にも経済的にも恵まれている家庭の出身者が多いため、そういった自分が経験したことのない現実に気づくことが難しいのです。前述の事例は極端な例かもしれませんが、教育現場には、支援を必要とするさまざまな児童・生徒がいます。その教室にいる一人ひとりを指導・支援していくためには、さまざまな視点でものごとを読み取り、分析していく力が非常に大切です。そのために、まず、自分の中にも偏った常識や偏見に気づくことが必要なわけです」。
アクティビティを通して体験的に気づく
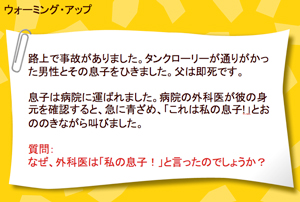 アクティビティを通して偏見に気づく
アクティビティを通して偏見に気づく出典:『地球市民を育む学習』(1997)明石出版
では、具体的にどのような方法で学生に気づきを与えるのでしょうか。大谷准教授は次のように話します。「前述のように、単に知識を教えるだけでは自分の中の偏見に気づくことは難しいと考えています。そこで、授業の導入では、さまざまなアクティビティを通して体験的に学べるように工夫しています。一例として、ひとつクイズを出してみましょう。『路上で事故がありました。タンクローリーが通りかかった男性とその息子をひきました。父は即死です。息子は病院に運ばれました。病院の外科医が彼の身元を確認すると、急に青ざめ “これは私の息子!”とおののきながら叫びました。なぜ、外科医は“私の息子”と言ったのでしょうか?(出典:デイビッド・セルビー, グラハム・パイク, 『地球市民を育む学習』,1997 )』という問題です」。
この問題は実際に授業の中で学生に出題したり、教員免許状更新講習で現役の教員に答えてもらうこともあるそうです。「たとえば、『外科医が離婚した妻との間にもうけた子どもだった』、『病院で取り違えた子どもだったことがDNA鑑定で判明した』というようなクリエイティブな答えが学生からも現役の教員からも多く出てきます。どちらも可能性としてないわけではありませんが、いちばん簡単で現実的な答えは、『外科医が母親だったから』ではないでしょうか。そう聞くと、多くの人が外科医を男性だと決めつけていたことにはっと気づくわけです。実際、教科書や教材などの写真やイラストで紹介される医師の姿は男性であることがほとんどです。私達は知らず知らずのうちにそういったイメージをすり込まれているのです」。
他にも、写真の一部を見せてその周りの情景を想像してもらうアクティビティや、母語と異なるルールやコンセプトで書かれた文章を読むのにどれだけ時間がかかるかを体験するアクティビティなど、気づきを得るためのさまざまな方法を実践しています。自分の偏見に気づくためには、体験的に学び、当事者の気持ちに気づいたり、これまで見えなかった自分のあたりまえがどういったものなのかを認識することが非常に大切なのです。そのような気づきがあってこそ、知識は実感を伴い、現実を理解するための手がかりとなります。「授業の話とは離れますが、留学してマイノリティの立場を体験してみるのも、とてもいい異文化トレーニングになります。特に多くの日本人は、お互いにあうんの呼吸で場の空気を読むようなところがあるので、自分の考えをしっかり主張しないと伝わらない海外では苦労することも多くあります。外国語で自分を表現することの大変さも思い知ると思います。しかしその体験こそが、多様な価値観に気づき、自分の中の“あたりまえ”を打ち破ること、つまり視野を広げることに効果的です」。
 大谷准教授オリジナルの活動「色ゲーム」
大谷准教授オリジナルの活動「色ゲーム」多文化共生で昨日より笑顔の多い世の中に
大谷准教授が異文化理解に興味を持った根底には、自身の小学生時代の苦い経験があると言います。「曾祖父が外交官だったこともあり、祖母はインド生まれのイギリス育ち、母は中国生まれと、外国に繋がりのある家庭で私は育ちました。日本の公立小学校に通ったのですが、家庭の文化と学校文化があまりに違うため、常に不安でした。当時は多文化共生という考えすらない時代ですから、仕方なかったのかもしれませんが、あらゆる場面で自分が劣等生であると感じさせられました。『失敗したくない、他の子と違うと思われたくない』と、いつも周囲の様子を見ながら、他の子の真似をしていました。それでまた「キョロキョロしている」と注意されてしまい、一時期は学校に行こうとするとお腹が痛くなったり、熱が出たりと、学校へ行けない状態になりました。そんな私が変われたのは、3年生の時に新しい担任の先生と出会ってからです。その先生は、私の創作した物語を見て『すてきなお話』とほめてくれたのです。それが嬉しくて、ほめられたくて、毎日お話を書いて先生に見せました。物語もだんだん長くなり、文章を書くことも楽しくなりました。それが自信となり、給食もたくさん食べられるようになって体力もつき、気づくと学校は楽しいところになっていました」。

つまり、教員にはそれだけの影響力があると言います。「教員が子どもをどう見るか、使う言葉の一つひとつにも、その子自身に大きな影響を与えます。また、先生の態度で、まわりの子がその子をどう扱うかも変わってきます。ほとんどの教員は一生懸命正しいと思うことをしているのですが、その“正しさの基準”は時代・立場や視点によって変わるものかもしれません。だからこそ、『自分の中には偏見があるかもしれない』という意識を持って、日々の自分の言葉や態度を客観的に振り返ることが大切なんだと思います。それは教員に限らず、あらゆる分野に当てはまります。それぞれの人々が、それぞれの立場で実行していくことが、いずれは社会の意識変化につながっていくと考えています。ただし、そうしたからといって偏見がこの世からなくなることはないでしょう。けれども、一人ひとりがそういう意識をもって生きることで、多文化共生は実現していくと思います」。









