鈴木美枝子先生「こどもまんなかの食生活支援」について考える(1)
2025.08.20
2025年6月27~29日に、第72回日本小児保健協会学術集会が金沢で開催されました。今回の学会で、私は「こどもまんなかの食生活支援―『幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイド』をもとに考える―」というシンポジウムを企画する機会を得ました。内容としては、2022年3月に作成された、厚生労働科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援にむけた効果的な展開のための研究」研究班(研究代表者:衞藤久美先生)の成果物である『幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイド【確定版】』(以下、支援ガイド)をもとに、どのように「こどもまんなか」の食生活支援をしていけばよいか、というテーマを掲げ、同研究班の先生方にご登壇いただき、多角的なアプローチを試みました。
この支援ガイドは、その前段階の「厚生労働省科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイドの開発に関する研究」研究班(研究代表者:石川みどり先生)の成果物をもとに、実際に支援者(保育者も含みます)への調査研究等を経て追加資料等を加えたものであり、作成のねらいは、保健医療従事者や児童福祉関係者等が、幼児期の栄養・食生活支援を効果的に展開していく上で共有すべき基本的事項や支援の方向性等を提示することとしています。
これらの研究班においては、管理栄養士、医師、歯科医師、などさまざまな研究分野の研究者が集い、あらゆる角度から幼児期の栄養・食生活支援について研究がなされました。私自身も研究分担者として、主に保育・幼児教育施設における食生活支援等について調査を重ね、保育・幼児教育施設での子どもの主体性を大切にした食生活支援―子どもの気持ちを大切にした偏食対応や、食の進まない子どもへの環境をも含んだ支援のあり方等―についても言及しています。
この支援ガイドは、こども家庭庁発足前に作成されましたが、子ども一人一人の様子を見ながら、多職種が同じ方向を向いて支援をしていくという点では、まさに「こどもをまんなか」にして支援をしていくことに通じるのではないかと感じています。実際、「目の前の子どもがどうか」という視点を大切にするために、支援ガイド(【確定版】)においてはQ&Aを付して、さまざまな支援場面を想定した対応等について数多くの事例を提示しています。支援者にとって支援の「引き出し」を増やすことで、目の前の子どもに対してどのようなかかわりをしていけばよいかについて考える材料にしていただければという思いで作成したものでもあります。
本シンポジウムでは、支援ガイド(【確定版】)の研究代表者の衞藤久美先生、研究分担者の多田由紀先生、船山ひろみ先生、そして鈴木美枝子がシンポジストを務めました。衞藤久美先生からは支援ガイドの概要について、多田由紀先生からは生活習慣からアプローチするこどもまんなかの食生活支援、船山ひろみ先生からは小児歯科の観点から口腔機能の発達に寄り添うこどもまんなかの食の進め方、そして鈴木美枝子からは保育・幼児教育施設におけるこどもまんなかの食生活支援について、それぞれの立場から発表しています。興味のある方はぜひ、第72回日本小児保健協会学術集会の参加登録の後、視聴期間内(8月22日まで)にご視聴いただけたらと思います。
参考文献
「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイド【確定版】」令和4年3月
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/youjishokuguide/YoujiShokuGuideKakutei.pdf
(2025年8月19日閲覧)
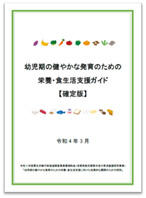
 こちらのQRコードからも閲覧できます。
こちらのQRコードからも閲覧できます。 第72回日本小児保健協会学術集会HP
https://nex-tage.com/jsch2025/(2025年8月19日閲覧)









