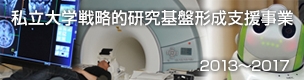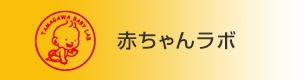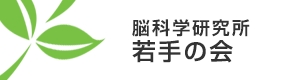6月27日(木)~29日(土)開催:玉川大学脳科学トレーニングコース2024-心をくすぐる技の共演-
玉川大学脳科学研究所では、脳科学研究を志す学部学生、大学院生、若手研究者を対象に、研究手法の基礎と応用を実習で学ぶトレーニングコースを開催します。本研究所所属の研究者を講師とし、また本学の研究施設を活用して、脳科学の研究手法の基礎と応用を実習と討論で学びます。
脳科学に興味と意欲を持つ皆さんの積極的なご参加を、心よりお待ち申し上げます。
| 日 程 | 2024年6月27日(木)~29日(土) |
|---|---|
| 会 場 | 玉川大学 脳科学研究所 |
| 対 象 | 学部学生・大学院生・若手研究者(文理不問・未経験者歓迎) 研究室見学ツアーのみの参加も可(定員外/要申込) |
| 受講料 | 3,000円(交通費・宿泊費は各自負担) |
| 実習コース |
|
| 共通カリキュラム (全受講者対象) |
|
| お申し込み |
専用ページからお申し込みください 各コースとも定員を超える場合には応募内容にもとづいて選考します。 |
| 締 切 | 2024年4月26日(金) |
| 主 催 | 玉川大学脳科学研究所 |
| 共 催 | 玉川大学大学院脳科学研究科 玉川大学大学院工学研究科 玉川大学学術研究所ミツバチ科学研究センター |
お問い合わせ
玉川大学脳科学トレーニングコース事務局
〒194-8610 東京都町田市玉川学園 6-1-1
neurocourse@tamagawa.ac.jp
受講者の声
げっ歯類を用いた脳システム研究法コース
私はこれまで、イメージング技術を用いた神経細胞の活動記録を主な研究手法として取り組んできました。新しい手法を学び、研究に新たな視点を加えることを期待して、玉川大学の脳科学トレーニングコースに参加しました。
げっ歯類を用いた脳システム研究法コースは、神経科学の歴史や実験技術についての講義から始まりました。ニューロピクセルや二光子イメージングの仕組み、ノイズ処理の方法などを詳細に学ぶことができました。特に、ブラックボックスになりがちな解析ソフトウェアの中身や、ニューロピクセル電極の実験系についての知識は、今後の研究に大いに役立つと感じました。二光子イメージングを用いた実習では、マウスに視覚刺激の提示を行いながら大脳皮質の神経細胞に導入されたカルシウムセンサーのデータを取得し、Suite2pで解析を行いました。この内容は早速自分の研究室で試しており、実験の精度や効率が向上し、大いに役立っています。また、ニューロピクセル電極を用いた実習では、開頭手術の実演や古典的条件付けされたラットのニューロン活動記録を見学しました。電極を刺入するとすぐにニューロンの活動が記録され、短時間の記録でも多数のニューロンの神経活動が得られることに感動しました。本トレーニングコースを通してニューロピクセルと二光子イメージングの両方を比較しながら実験を行うことで、各手法の特徴をより深く理解することができました。 また、このトレーニングコースは少人数での指導体制が取られており、個別の疑問点をその場で解消できたことが大変ありがたかったです。先生方とのディスカッションも活発で、貴重な機会となりました。ニューロサイエンス全体にわたるさまざまな話題についての議論を行うことができ、非常に刺激的な時間を過ごすことができました。さらに、懇親会の時間も豊富に設けられており、他大学や研究機関の学生や研究者と交流することで、異なる視点や考え方に触れることができました。この交流は、新たなインスピレーションを得るとともに、将来的な共同研究の可能性も感じさせるものでした。
短期間ではありましたが、非常に濃密で有意義な時間を過ごすことができました。最後になりましたが、お忙しい中ご指導いただいた先生方、スタッフの皆様、そして関係者の皆様に心から感謝申し上げます。このような貴重な機会を提供していただき、本当にありがとうございました。
早稲田大学先進理工学研究科 山田 貴巨さん
霊長類の行動・神経科学実習コース
私がこのプログラムに参加した理由は、霊長類を用いた神経科学におけるウェット(in vivoイメージング・電気生理学的手法)、及びドライ(モデリング・データ解析)の一連の実験手法について学びたかったからです。私はこれまで、培養細胞などをモデルとして神経細胞生物学の基礎研究に従事してきました。そのなかで、大学院ではヒトでみられるより高次な脳機能がどのように創発されるのかについて、霊長類を用いて研究することに興味を抱くようになりました。そのような中、「霊長類のウェットな実験技術」と「計算論的神経科学の基礎」を同時に学ぶことができる本コースに魅力を感じ、すぐに応募を決めました。
3日間のトレーニングコースはとても充実しており、たくさんの学びを得ることができました。初めに、霊長類を用いて脳科学研究をすることの意義、霊長類の脳科学で使用されている実験手法やよく研究されている研究テーマについて広く学ぶことができました。こうした講義を拝聴するなかで、ヒトと進化的な近接性・相同性が高いことが霊長類を用いることの大きな利点であり、高次な脳機能を調べるのに有用なモデル生物だということが改めて理解できました。
次に、霊長類の脳科学実験に用いられている先端的な実験設備、実験器具、さらに実際の電気生理学実験の様子を実際に見学することにより、霊長類を用いた脳科学実験が現場でどのように展開されているのかについて具体的に理解を深めることができました。加えて、コンピュータを用いた神経科学のドライな研究手法についても、実際にプログラムを実行しながら学ぶことができました。「脳の内側から外側を視る」計算論的神経科学のアプローチは脳の機能を構成論的に記述するのに有用であることがよく分かり、今後更に深く学んでいきたいと思いました。
最後に、本トレーニングコースでは、同じ分野のコースに参加した方々はもちろん、他のコースの参加者とも交流できる機会が数多く用意されていました。本トレーニングコースの参加者はバックグラウンドも多様であり、これまで知らなかったような研究内容や実験手法について様々なお話を伺うことができ、非常に刺激的な経験でした。また、このコースは参加者が少ないという性質上、全体として教員の方々とも距離が近く、カジュアルに質問しやすい雰囲気であるように感じました。私自身、大学院進学に関わる悩みなど実習とは直接関係のない相談までさせていただき、将来のキャリアを考えるにあたって貴重なアドバイスをいただきました。本コースを受講することで、「霊長類の神経科学」、「計算論的神経科学」について体系的に理解を深めることができました。特に、ウェット、ドライのアプローチを一連の実習の流れの中で並列的に学ぶことにより、自分で実験を組み立てているような新鮮な感覚で実習に取り組むことができました。また、著名な講師の方々や様々なバックグラウンドをもつ受講者の方々との活発な交流により、自分の知識の幅を広げることができました。最後になりましたが、お忙しいなか本トレーニングコースを企画・運営してくださった玉川大学脳科学研究所の方々に改めて感謝申し上げます。
埼玉大学理学部生体制御学科 鴇崎 皓紀さん
ヒトのfMRI基礎実習コース
私は、無意識をテーマに研究を行っており、現在は実験経済学の中で視線計測という認知的なアプローチを用いて研究をしています。卒業後は視線にとどまらず、脳の賦活を分析することにより、人間の意識についてより深くアプローチできないかと考え、「ヒトのfMRI 基礎実習コース」に応募しました。
本コースは、大きく分けて3つの内容について学ぶことができました。
1つ目はfMRIについての講義、2つ目は脳解剖についての講義、3つ目はグラフ理論についての講義です。fMRIについては、はじめにresting state fMRIの計測を参加者全員で行いました。fMRIや周辺装置・周辺器具についての説明の後、1人づつ計測を行い、計測中、被計測者以外の他参加者は計測方法や計測における注意点等について簡単に学びました。計測の後、松田先生によりfMRIの特徴や仕組み、実験デザイン等についてご講義いただきました。自分で勉強する中では理解していなかったことも深く学ぶことができ、実際に身をもって計測を行った後にfMRIについて詳しく学べたことで実感を持って学ぶことができました。また、取得した自身のデータをfMRIにより解析しました。解析の中ではエラー等も幾度か出ましたが、先生方が丁寧に監督してくださったこともあり、解析においてそれぞれの設定が持つ意味を学びながら、参加者全員が各々、自身のresting state fMRIデータの賦活について確認することができました。
2つ目の脳解剖についての基礎講義ですが、こちらはfMRIのデータ解析を行う前に、解析にあたって脳についてある程度理解をするという趣旨で、松元先生により行われました。脳の各部位や成り立ちについて学ぶことができ、fMRIによって取得したデータを分析する上で脳についての理解を深めることができました。大学での基礎的な神経科学の受講経験はありましたが、脳が成り立っていく過程について初めて詳しく学ぶことができ、勉強になりました。
3つ目のグラフ理論についての講義は田中先生により行われました。講義では分かりやすい具体例を用いたグラフ理論の概念的理解に始まり、特定の基準に従った二値変換であるThresholding、正準相関分析に至るまで取り扱われました。グラフ理論については経済学でもマッチングの分野で用いる場合があるのですが、今までしっかり学習できていなかったこともあり、自分の中にない思考法・手法を取り入れることができ、勉強になりました。
本コースの受講により、自分がfMRIを用いた先行研究を読む上での理解を深めたことは勿論のこと、知識の向上のみならず、身をもってデータの取得・分析を行う機会を得たことで、今後fMRIを自分の研究でどの様に用いるかといったイメージが格段に向上しました。このような貴重な機会を設けていただき、丁寧な指導をしてくださった先生方および関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
中央大学大学院経済学研究科 杉本 大樹さん
社会科学実験手法コース
私は、法的な場面における道徳的判断および神経基盤に焦点を当てた研究を行っています。ヒトの処罰や救済行動に興味があり、向社会行動と関連の高いオキシトシンの解析方法を学ぶ目的で本コースに応募いたしました。
1日目の前半は、高岸先生よりオキシトシンの神経生理学的な知見について解説いただきました。講義を通じて、オキシトシンと他者への信頼行動、精神的・身体的健康、および受容体遺伝子との関連について包括的に学びました。この知識を得たことで、自身の研究テーマにどのように応用できるかを明確に意識できるようになりました。その後、実際に自身の唾液を採取してオキシトシンを解析するため、生化学解析室に移動しました。ELISAキットやピペットを用いて前処理まで行い、唾液採取の際の注意点や使用するキットについての説明を受けました。ここで得た情報は、後に自分で環境を構築する際に非常に役立つものだと感じました。
2日目の初めは、oTreeを用いて事前にプログラムされた社会科学実験の信頼ゲームを体験しました。その後、田中先生よりoTreeの概要や特徴、そして信頼ゲームと1日目に講義していただいたオキシトシンとの関係について解説いただきました。講義により知識を体系化した後、先ほど体験した信頼ゲームのプログラムを一から作成しました。プログラミングは、説明を受けた後、実際に手を動かして作業を行うハンズオン形式で進められたため、安心して取り組むことができました。プログラムの作成からサーバーへのアップロード方法まで一連の流れを教えていただいたため、後日、個人的に別のプログラムを作成した際もスムーズに作業を進めることができました。一日の後半は、前日に前処理を終えたオキシトシン解析の準備を引き続き行い、最終的に得られたOD値から標準曲線を描いて解析しました。解析までの準備は繊細な作業の繰り返しだったため、結果が標準曲線に反映される際は非常に緊張しました。
3日目は、トレーニングコースの受講者全員によるJam sessionでした。テーマは「言語はどのように発現していくか」について、トランプカードゲームを通して議論することでした。バーバル・ノンバーバルコミュニケーションが禁止された状況下で、ペアとなった相手と同じマークのトランプカードを「合意に基づいて」同時に提示できるよう探求しました。その後、少人数のチームを組み、ゲーム中にどのような合意が形成されたのか討論しました。研究分野が異なるメンバーで構成されたチームだったため、議論には共通する点もあれば、異なる点もあり、非常に興味深かったです。
全体を通して、トレーニングコースでの研修が「自分で一通り実施可能になる」という目標を達成するプログラムとなっていました。また、知識や技術の習得のみならず、懇親会やお昼休みを通じて様々な研究分野の方々と情報を共有できたことは、今後の研究生活にとって非常に有意義なものとなりました。ご多用の中、3日間という限られた時間で我々受講者が最大限の学びを得られるよう尽力いただいた諸先生方ならびに大学院生の皆様に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
総合研究大学院大学 生理科学専攻 花田 捺美 さん
赤ちゃん研究実習コース
私は、重度肢体不自由児の愛着行動に関する研究を行っています。今回、赤ちゃん研究の分野でご活躍されている玉川大学の先生方から、乳幼児の行動および生理指標の計測・解析・解釈の基礎および実践について学びたいと思い、玉川大学脳科学トレーニングコース(赤ちゃん研究実習コース)を受講しました。
本コースは3日間にわたって開講され、1日目と2日目には、赤ちゃん研究に関する専門的かつ実践的なプログラムが行われました。プログラムの冒頭では、まず、子どもを対象とした観察研究を行う際の視点について、子どもが絵本を読む場面を例にご講義いただきました。1枚の静止画に対する解釈を参加者間で共有することを通して、観察者により着眼点が異なることや、観察手法により得られる情報の量や質が異なることを体感することができました。その後、赤ちゃんを対象とした研究を行うための施設「赤ちゃんラボ」にて、実際の計測の様子を見学しました。赤ちゃんの行動をリアルタイムでモニターするための計測環境設定や、赤ちゃんに負担を与えない心電計の着脱方法に加えて、計測状況に応じた臨機応変な対応や限界点についても直に学ぶことができました。さらに、計測後の行動、音声、心拍、脳波のデータ解析手法について学び、解析を実際に体験することもできました。最後には、行動データの解析結果を発表し、先生方からご講評をいただくことができました。
3日目には、他分野の方との合同プログラムが行われました。他分野の方との合同グループで言語の形成過程を体験するゲームを行った後、ゲームでの気づきをもとにディスカッションを行いました。私自身は主に言語発達や相互作用の視点に基づき意見することが多かったのですが、他分野の方からは人類学や統計学に基づく意見があり、分野横断的に視野を広げるよい機会となりました。
以上のような充実したプログラムに加え、懇親会や休憩時間にも先生方や他の受講者の方々と交流や意見交換をすることができ、大変濃密な3日間となりました。温かくご指導いただきました岩田先生、梶川先生、佐藤先生、佐治先生、大学院生の大豆生田さんをはじめとする玉川大学脳科学研究所の皆様、ともに学んだ受講者の方々、実験にご協力いただきました保護者および乳児の皆様に、心より感謝申し上げます。
北陸大学 長森 由依さん
VRを活用したロボット実験実習コース
私は、認知バイアスを解きほぐしたり、客観的な視点を獲得する方法に興味があり、テクノロジーを活用することでこれらの能力を促進できるのではないかと考えています。現在、人と関わるコミュニケーションロボットの研究に従事しており、ロボットとのインタラクションという視点から自身の興味に対する研究に取り組んでおります。玉川大学トレーニングコースを受講した理由は、普段は実空間でのロボットを用いた研究を行っていますが、今後はVR空間を用いたアプローチも取り入れたいと考えているためです。そのため、技術面の強化が必要だと感じ、トレーニングコースを受講しました。
1日目は、稲邑先生からご自身が取り組んでいらっしゃる研究背景を踏まえ、本トレーニングコースで使用する仮想空間内にてロボットとインタラクションを行うことができるプラットフォームであるSIGVerseについて説明を受けました。まず、SIGVerseがUnityエンジンを基盤として動作することを理解し、準備されたチュートリアルを参考にUnityの基本的な使い方について確認しました。その後、仮想環境内でのアバターの基本的な操作方法について学び、自身のアバターをデザインし、これを用いて、HMD内にて自身が作成したアバターを仮想空間内で操作するところまで行いました。1日目では、実際に手を動かしながらSIGVerseの基本的な機能について学ぶことができました。
2日目の実習では、1日目に学んだ基本的な内容を踏まえて、本実習の目的である仮想空間内にて、自作のアバターを用いてロボットとインタラクションを行うための方法について学びました。ロボットの制御を行うためにはロボットのオペレーションシステムであるROSとの統合が必要であり、まずはROSについての説明を受けました。その後、仮想環境内でのロボットとインタラクションを行うための手順やインタラクション時のロボット及び人の行動の記録・分析方法について具体的に学びました。実習の合間には、仮想環境から現実空間内に設置されているロボットを操作するといった体験などもさせていただきました。実習を通して、SIGVerseの汎用性の高さやシステムとしての充実さを実感することができました。最後に、実習参加者が取り組んでいる研究をSIGVerseを使ってどのように発展させることができるかについて、稲邑先生とディスカッションを行いました。
今回の実習を通して、仮想空間でのロボットとインタラクションを行うための技術について触れることができ、とても貴重な経験を得ることができきました。今後の自身の研究を行うための非常に有意義な時間となりました。お忙しところ、企画運営・ご指導いただきました諸先生方ならびにスタッフの皆様に、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。
大阪大学 末光 揮一朗さん