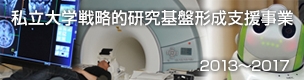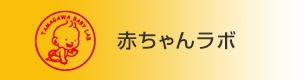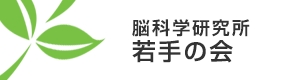6月19日(木)~21日(土)開催:玉川大学脳科学トレーニングコース2025 〜心をくすぐる技の共演〜
玉川大学脳科学研究所では、脳科学研究を志す学部学生、大学院生、若手研究者を対象に、研究手法の基礎と応用を実習で学ぶトレーニングコースを開催します。
脳科学に興味と意欲を持つ皆さんの積極的なご参加を、心よりお待ち申し上げます。
| 日 程 | 2025年6月19日(木)~21日(土) |
|---|---|
| 会 場 | 玉川大学 脳科学研究所 |
| 対 象 | 学部学生・大学院生・若手研究者(専門分野不問・未経験者歓迎) 定員超過の際は応募資料により選考します。 |
| 受講料 | 3,000円(交通費・宿泊費は各自負担) |
| 実習コース |
|
| 共通カリキュラム (全受講者対象) |
|
| お申し込み |
専用ページからお申し込みください 各コースとも定員を超える場合には応募内容にもとづいて選考します。 |
| 締 切 | 2025年4月25日(金) |
| 主 催 | 玉川大学脳科学研究所 |
| 共 催 | 玉川大学大学院脳科学研究科 |
お問い合わせ
玉川大学脳科学トレーニングコース事務局
〒194-8610 東京都町田市玉川学園 6-1-1
neurocourse@tamagawa.ac.jp
受講者の声
げっ歯類を用いた脳システム研究法コース
- げっ歯類コースは、脳科学研究所田中研究室でげっ歯類を用いた実験手技および解析方法を中心に見学、体験できるものでした。1日目は、講義に加え、ラットの開頭手術とイメージング実験を見学しました。2日目には、電気生理学的記録を見学し、その後、イメージングおよびスパイクデータの解析を体験しました。3日目は、他コースの受講者も交えた"Jam Session"や研究室見学が実施され、幅広い交流の場となりました。また、先生方との懇親会も設けられ、研究を行う上での精神や研究室の空気感をも肌で感じる大変貴重な機会となりました。(防衛医科大学校医学科・仁科友希さん)
- 本コースを選択した理由は、げっ歯類における神経記録の最先端手法を体系的に学ぶためです。マウスやラットは、遺伝子改変や神経操作が比較的容易で、神経科学分野で広く用いられており、多様な計測技術や操作法との組み合わせが可能です。特に近年では、より多数の神経細胞から活動が取得されています。本コースでは最先端の記録法、およびそれらのデータ解析までを一貫して学べる点に大きな魅力がありました。 (大阪大学大学院医学系研究科 山本拓都さん)
- 実習では、げっ歯類の生体における神経活動記録に関して、2種類の手法を見学しました。2光子顕微鏡を用いた実験では、マウス脳において遺伝的蛍光プローブで標識した神経細胞から自発的な活動を記録する様子を見学しました。電気生理実験では、Neuropixels電極を用いて、課題遂行中のラットの神経活動を細胞外から記録する様子を見学しました。さらに、これらの手法により取得したデータに対する解析手法(ノイズ除去や解析に適した形式に整えるといった前処理や、神経活動を元にした細胞の分類など)を学ばせていただきました。(同志社大学心理学部 町井志帆さん)
- 実験デザインの立案から、電極挿入のための手術、得られたデータの前処理に至るまで、論文を読むだけでは得られない、実践的な疑問や発見がありました。目の前で進行する実験に関して持った様々な疑問にも、その場で解決策をご教示くださり、2つの計測手法の類似点や相違点について考えることができました。(筑波大学大学院ニューロサイエンス学位プログラム 松本悠雅さん)
- 実習に参加して、研究手法の選択や解析の工夫が成果に直結することを実感しました。最終日のJam Sessionでは、少人数のグループで認知科学のテーマについて議論し、さまざまな視点に触れられたことが印象的でした。多様な考え方や技術を組み合わせる重要性を改めて感じ、今後の研究に向けて大きな刺激を受けました。(奈良先端科学技術大学院大学 内田朱音さん)
- 今回のコースを通じて、最先端の研究手法を実際に体験し、解析技術を身につけることができました。また、トレーニングコース最終日には様々な研究室を見学させていただき、脳科学研究所が工学・生物学・化学など多様な視点から脳を研究していることに深い感銘を受けました。さらに、大学院では奨学金制度が整っていることも知ることができ、研究内容とあわせて、玉川大学の魅力を改めて実感する機会となりました。重ね重ねになりますが、今回のコースで丁寧にご指導くださった田中先生、青木先生、杉本先生に、心より感謝申し上げます。(東京農工大学工学部 張替 琢生 さん)
霊長類の行動・神経科学実習コース
私は現在、齧歯類を用いた研究に従事していますが、学部時代はヒトを対象とした実験に関わっていたこともあり、両者の中間に位置する霊長類研究についてより深く学びたいと考え、本コースへの参加を決めました。齧歯類とヒトの研究の共通点・相違点を理解するためにも、霊長類というモデルを実際に体験することは、自身の研究視野を広げるうえで非常に有意義だと感じました。
受講前に配布された各コースのテキストブックは写真や図が豊富で、実験の具体的な様子を事前にイメージすることができました。「実物を見てみたい」というモチベーションが高まり、実習にもより深く没頭できたように思います。
コース中は、手術室の見学や、手術キットを用いた筋電図電極の埋め込み手術練習、行動課題に取り組むサルの観察、脳切片作成、ECoGを用いた脳情報のデコーディング、強化学習シミュレーションなど、多岐にわたる実習を経験しました。さらに、霊長類を対象とした遺伝子操作、モデルベース解析、生体記録技術、神経・筋活動計測などの講義を通じて、理解を深めることができました。個人的に、齧歯類やヒト研究と比較しながら受講していたので、霊長類特有のアプローチや意義を実感でき、非常にエキサイティングな体験となりました。
また、分野や所属の異なる参加者や玉川大の学生と交流する機会も多く、懇親会では「こうした出会いが将来につながることも多い」と複数の先生方がおっしゃっていたのが印象的でした。今回のトレーニングコースは、知識・技術の習得にとどまらず、研究者としての視野を広げ、人とのつながりを深める貴重な機会となりました。このような場に参加できたことに深く感謝しています。
(東京大学総合文化研究科 三浦あゆな さん)
ヒトのfMRI基礎実習コース
私は、スポーツのパフォーマンス分析に関する研究を行っています。これまでは主に位置情報や行動データを扱ってきましたが、競技中の動作や判断が脳活動とどのように関係しているのかにも関心があり、脳内の情報処理にも着目したいと考えるようになりました。fMRIを自ら体験しながら学ぶ機会を得たいと思い、「ヒトのfMRI基礎実習コース」に参加しました。
実習では、まず参加者自身が被験者となって、安静時の脳活動をfMRIで撮像しました。fMRIの原理や撮像時の注意点について講義を受けた後、順番に装置に入り、実際に計測を行いました。作動音の大きさや装置内の圧迫感など、被験者として体験して初めて分かる感覚も多く、実験設計における被験者への配慮の重要性に気づかされました。
続いて、fMRI解析に必要な脳の構造や機能について、松元先生から脳解剖学の基礎を学びました。解剖学的な視点を取り入れることで、後の解析で観察する脳領域の意味や位置関係をより深く理解することができました。
また、松田先生による講義では、fMRIの基礎、安静時脳活動に関する理論的背景、および解析手順についてのレクチャーを受けました。その後、自身の安静時脳活動データを用いて解析を行い、可視化された脳画像から後部帯状回、楔前部、内側前頭前野、下頭頂小葉といった領域を確認しました。これらは、安静時に相関して活動が増加するDefault mode networkを構成する代表的な脳領域であり、時間的に似た活動パターンを示すことで機能的に結び付いているとされます。講義で理論として理解していた概念を、自分の脳活動に基づいたデータを通して視覚的に確認できたことは、大きな学びとなりました。
さらに、田中先生による講義では、脳をネットワークとして捉えるグラフ理論の考え方について学びました。脳領域をノード、領域間の機能的結合をエッジとして表現し、その構造的特徴を定量化する手法について理解を深めました。
本実習では、fMRIの撮像から解析、ネットワーク分析の基本までを一貫して体験することができ、自分の研究分野を広げるうえで非常に意義深い経験となりました。今後はスポーツ科学と脳科学をつなぐ視点を活かし、動作や位置情報だけでなく、脳活動を含めた多角的な分析を進めていきたいと考えています。
このような貴重な学びの機会を提供してくださった松田先生、松元先生、田中先生、ならびに院生の方々、スタッフの皆様に心より感謝申し上げます。
(立命館大学情報理工学部 目 淑乃 さん)
赤ちゃん研究実習コース
私は、乳児と養育者それぞれの感覚特性が、両者のインタラクションに与える影響に関心を持っています。さらに、そのインタラクションの積み重ねが、養育者-乳児間のアタッチメントや乳児の情動調整の形成にどのように関わるのかについて研究しています。本トレーニングコースを受講したのは、養育者-乳児間のインタラクションを映像記録や生理指標(心拍や脳波)を用いて捉える手法を身につけることで、そのダイナミクスを可視化し、自身の研究をより豊かにできると考えたからです。
1日目では、岩田先生より「絵本を読むこと」の発達的意味についてご講義いただきました。実験室の中で見えることと、実際の生活文脈の中で見えることの違い、そして、まだ多くの言葉を持たない乳児が、細かな動作や表情を通して豊かな「ことば」を発しているという視点に触れ、乳児の行動を丁寧に読み取る重要性を改めて感じました。
ELANの実習では、佐藤先生よりジェスチャー研究の歴史や現状をご講義いただき、ELANを用いた行動解析の方法について、具体的な操作を交えながらご説明いただきました。また、サンプルデータを用いて、受講者それぞれの視点で分析を行い、2日目に結果・考察を共有することで、解析の練習だけでなく、研究者によって注目する視点や捉え方が異なることを実感しました。梶川先生からは、音声分析の基礎を教えていただき、親の発声と子どもの動きから、親子の相互情動調整を読み取るということを学びました。
さらに、佐治先生からは、心拍や脳波を導入したELANでの分析についてご教示いただき、行動と生理の両面からインタラクションを多角的に捉える方法を学びました。また、玉川大学脳科学研究所の赤ちゃんラボを見学させていただき、実際の研究現場の雰囲気に触れることができました。特に印象的だったのは、佐治先生が保管されていた、分厚い紙媒体の心拍・脳波データを見せていただいたことです。今ではコンピュータ上で数値化されているデータが、かつては手作業で手間をかけて記録されていたことを知り、研究の積み重ねとデータの重みを強く感じました。同時に、データを自身で取る過程にどれだけの労力と意義があるかを実感し、今後自分自身が実際にデータを取る際にも、その大切さを忘れずに取り組みたいという思いを新たにしました。
3日間を通して、非常に実りある学びの機会をいただきました。今後は、このトレーニングで得た知見や技術を活かし、養育者と乳児の行動や感覚特性に対する理解をより深める研究を進めていくことを目標としています。最後になりましたが、お忙しい中、丁寧にご指導・運営くださった先生方に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
(京都大学教育学研究科 村山 新さん)
VRを活用したロボット実験実習コース
2025年度第14回脳科学トレーニングコースにおいて、私は「VRを活用したロボット実験実習コース」に参加させていただきました。
私は現在、他大学の学部四年生で卒業研究を進めている最中であり、その中でVR技術を扱う必要があったため、充実した実験環境でハードウェアやソフトウェアに関する基礎知識や研究のヒントを得られることを期待して本コースに申し込み、選考の結果、ありがたいことに受講資格を得ることが出来ました。
実際のコースの内容は予想以上に刺激的かつ面白いもので、たいへん実りあるものでした。1日目は座学に始まり、おおよそ1時間ほど経ったあたりから実機を用いた実践形式の演習に切り替わりました。また2日目に関してはそのほとんどが体験型の実習で、VR(Virtual Reality:仮想現実)空間内の仮想アバターを介して実世界のロボットを操作する技術や、最新のHMD(Head Mounted Display)を用いたAR(Augmented Reality:拡張現実)ゲーム、アイトラッキング(視線追跡)、HCI(Human Computer Interaction)などの技術を体験することが出来ました。このARとアイトラッキングは、コース担当の稲邑哲也先生が1日目の冒頭に参加学生の興味を聞いて、急遽プログラムを改変して導入してくださったものであったため、その柔軟かつ寛大な対応がとてもありがたかったです。
加えて他の参加者との交流も楽しいものでした。VRを扱うコースということもあり、私と同じような工学部に所属する男子学生ばかりだと予想していたのですが、参加者四人のうち半分が女子学生かつ心理学を専攻しており、更には半分が留学生というたいへんバックグラウンドが多様なメンバー構成となっていました。皆が社交的で、積極的に違った視点からアイデアや疑問を出し合うため、打ち解けるまで時間はかからず、最初から最後まで充実したトレーニングになっていました。
初めは3日間というボリュームの多さに圧倒され、最後までやり遂げられるか不安でしたが、実際にはあっという間でした。それでいて収穫の多いものでした。このトレーニングで得た知識や技術、人脈は間違いなくこの先のキャリアに活きると思います。脳科学に興味のある意欲ある学生、研究者の方々にはぜひともこのトレーニングコースに参加してほしいです。また私自身も機会があれば他のコースも受講してみたいです。
(宮崎大学工学部 小久保 廉汰さん)