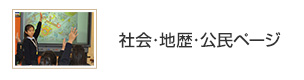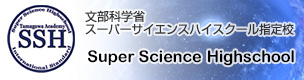玉川大学文学部人間学科高大連携授業
1月26日(月)、11年(高2)PLクラスの生徒を対象に、玉川大学文学部人間学科の長谷川洋二先生による授業がおこなわれました。テーマは「異文化とともに生きる」でした。いま、まさに世界で叫ばれていることですが、それを困難にさせているのは何でしょうか?それを考えるのが今回のテーマです。
この高大連携授業は、あるテーマを通して、大学の先生とディスカッションをすることにより、今まで学習した内容や考え方がどのように先端科学・研究内容に関係しているのかを知り、さらに今までにない新しい見方、考え方に触れることによって、概念理解の深化や探究心の育成をめざしています。
また、大学の先生と高校教員が協働して授業を展開し、教材開発や指導法の工夫をおこなっています。
生徒はいつもと違った授業展開に戸惑いながらも、大学の先生の問いかけに積極的に答え、高度な議論が展開されていきました。授業の事前・事後に課されたレポート課題にも生徒同士議論しながらまとめていたのが印象的でした。
今年度は、3回の授業がおこなわれました。
第1回 5月16日(金) 玉川大学文学部人間学科 岡本裕一朗先生
テーマ「環境倫理学の問題提起」
第2回 7月 8日(火)玉川大学文学部人間学科 林大悟先生
テーマ「脳死・臓器移植と人体の資源化」
第3回 1月26日(月)玉川大学文学部人間学科 長谷川洋二先生
テーマ「異文化とともに生きる」
生徒の感想を紹介します。
普段の授業より掘り下げて考える授業でおもしろかった。高校の授業と違い、覚えるというより考える授業だった。大学の授業は難しい。大学の先生は興味を持たせるように授業を展開してくれる。時間があっという間に過ぎた。一つの問題に対して、意見が分かれ、それについて議論する授業は非常に有用だと思います。大学の先生は板書をあまりしないので、聞き漏らさないように授業を受けなくてはいけないのでたいへんでした。3回の授業で物事の本質をどう見極めるかを、少し身につけられたと思います。
- 玉川大学文学部HPはこちら →
- http://www.tamagawa.ac.jp/humanities/