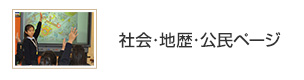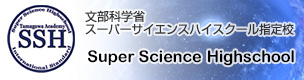「第63回日本学生科学賞」東京都大会で、10年生から12年生の6名が優秀賞ならびに奨励賞を受賞
2019年10月26日、「第63回日本学生科学賞(読売新聞社主催)」東京都大会の表彰式が行われ、優秀賞ならびに奨励賞に選ばれた10~12年生6名が出席しました。
「日本学生科学賞」は未来の優秀な科学者育成のために創設され、理科教育では日本で最も伝統のあるコンクールです。毎年、本学園では、クラブ活動の一環としてサイエンスクラブやサンゴ部が応募している他、選択授業スーパーサイエンスハイスクール(SSH)リサーチ科学と自由研究の物理班、化学班も参加しました。
今回は、優秀賞に11年生の廣瀬杏奈さんと10年生の平野悠さんの研究内容が選ばれ、12年生の柴田蔵人さん、古川モア奈さん、山本萌絵さん、10年生の赤塚暉洋さんの研究が、奨励賞を受賞しました。
 左から 赤塚さん、山本さん、平野さん、廣瀬さん、古川さん、柴田さん
左から 赤塚さん、山本さん、平野さん、廣瀬さん、古川さん、柴田さん読売新聞東京本社ビル内「よみうり大手町小ホール」で行われた表彰式の様子とともに、入賞した皆さんの研究成果を紹介いたします。
優秀賞:11年生 廣瀬杏奈さん
「打点式記録タイマーの問題点は」

授業で行った重力加速度の実験で正確に測ることのできなかった打点式記録タイマーを放電式記録タイマーと比べながら問題点を探りました。
放電式記録タイマーの精度や重さの違いによる変化を確認してから、放電式と打点式を同時に使い、打点式記録タイマーの打点周期の変動や落下物の加速度への影響について、実験スタンドを利用した場合と固定した場合と異なる状況下で、100gと1kgの重りを使って比較し、1打点ごとに振動の影響を測定しました。
結論として、質量が小さいと摩擦の影響で加速度に変動が生じて打点式記録タイマーでは±の振動が、放電式記録タイマーでは減少して戻る振動が現れました。質量が大きくなると加速度に影響は出ないが、打点式記録タイマーは実験スタンドが揺れたり、記録テープの早さが2.5m/sを超えると打点周期が乱れることなどが判りました。
今後は実験スタンドの揺れによる影響や、打点式記録タイマー単体で高精度に測る方法を考察していきたいと思います。
優秀賞:10年生 平野悠さん
「野菜切断面の変色理由を探る」

昨年の研究で、レタスの茎を切る際に出る「白い液体」が変色に関係していることがわかり、レタスの他に断面から白い液体が出るサツマイモをレタスと比較しながら変色原因を調査しました。
レタスの茎の切り口が赤く変色する原因は、レタスに含まれるポリフェノール(クロロゲン酸)が、白い液体(ポリフェノール酸化酵素)と空気(酸素)に触れることによって、クロロゲン酸が酸化され赤く変色することがわかりました。また、サツマイモの変色は、白い液体に含まれるポリフェノール(クロロゲン酸)、グルタミン酸、ポリフェノール酸化酵素が空気(酸素)と触れるためで、グルタミン酸が多く含まれていることから赤ではなく茶色に変色することがわかりました。
クロロゲン酸にグルタミン酸が混ざることで、クロロゲン酸の酸化反応に変化が生じるのではないかと考察しましたが、そのメカニズムが明らかにできていないため、さらに研究を進めていきたいと思います。
平野さんは、第61、62回2年連続で最優秀賞を受賞。今年度も優秀賞と研究の成果を残しました。
奨励賞:12年 柴田蔵人さん
「振動止めの効果についての研究」
怪我の防止となり、テニスラケットなどに装着し使用する振動止めは、振動をどのくらい抑えているのか、形状によって効果に違いがあるかを実験し、怪我の防止につながる形状を模索しました。
方法は、ボールの位置からラケットまでの高さが5mに設置できる装置からボールを自由落下させ、加速度センサーによって加速度を測定することで振動を定量化できるように工夫して実験しました。
振動止めの種類と加速度の大きさを比較して関係性を解析した結果、質量と振動の大きさには反比例の関係があることがデータによって示されました。
結論として振動止めには、よく振動を抑える効果があるものと、ある程度押さえるものの2種類があり、ひも状のものとグリップに装着するタイプは振動をよく抑え、円形型の振動止めは振動を抑えて怪我を防止する効果が高くなることがわかりました。
奨励賞:12年生 古川モア奈さん
「おいしい昆布だしを取る方法」
和食に欠かせない出汁に着目し、おいしく手軽に昆布だしをとるための条件を検証しました。
昆布だしの取り方は、漬け置き作業に関しては時間と水温、加熱作業は時間、温度、昆布の形状、水の硬度の条件を変えて検証を行いました。
結果、1時間以上常温の水またはお湯で漬け置きをし、沸騰直前まで加熱することで、より多くの旨味成分であるL-グルタミン酸を抽出することができました。また昆布の形状はL-グルタミン酸の抽出量に関係がないこともわかりました。
研究を通し、一般的な昆布だしのとり方が、L-グルタミン酸を最も多く抽出できることがわかりました。昆布は長時間水に漬けることによって膨張し、細胞壁が破壊され、多くのL-グルタミン酸を抽出できます。一方でL-グルタミン酸は耐熱性がないことから、加熱しすぎると減少させてしまうと考えられます。また、冷凍、冷蔵、室温のいずれの保存方法でも、L-グルタミン酸量が減少することがわかりました。
奨励賞:12年生 山本萌絵さん
「調理による食品中鉄含有量の変化」
私は、陸上部の練習中に貧血と思われる症状になってしまい、貧血の原因について調べたところ、鉄分不足であることがわかりました。鉄分入り健康飲料と鉄分の含有量が高い小松菜に着目し、鉄分量を減少させることなく食べられる調理法を科学的に検証しました。
まず、鉄分入り健康飲料を加熱し、温度によって鉄分量に変化がないことを確認しました。次に、小松菜を茹でる時の温度、時間、小松菜を入れるタイミング、小松菜の切り方、水量、水の硬度を変え、1-10フェナントロリン法により茹で汁に含まれる鉄濃度を測定し、比較しました。
その結果、小松菜は茹でると鉄分が茹で汁に溶け出してしまうため、なるべく硬度の低い水で短時間茹でる方が良いことがわかりました。また硬水ほど鉄分が溶けやすい理由としては、硬水に含まれる金属イオンが小松菜に浸透し、小松菜の鉄イオンが出てくるためだと考えられます。塩茹ですることで色を保つ効果はありますが、鉄分量を減少させてしまうこともわかりました。
奨励賞:10年生 赤塚暉洋さん
「環境にやさしい水力発電」
ダムを作らず、環境にやさしい方法として、時流式である水力発電を用いた場合のモーターの変換や、発電量と使われない水流のエネルギーの関係について検証しました。
水を流して水車を回し、発電量とそのとき使用されていない水のエネルギーの割合を調べました。モーターの一方に電池、もう一方に負荷をつけて変換効率を測った結果、電気・力学の変換率は70%弱でした。また水車の軸に様々な重さの測りをかけ、そのトルクに対応する水車の回転速度を測りました。
結果、水車は負荷側のトルクを上げると回転速度は下がり、モーターの回転数が一定であれば負荷と発電量は反比例します。ところが、水車の発電システムでは負荷を下げると発電機を回すトルクが上がり、回転速度も下がり発電量も下がるので発電量が最大になる回転数がありました。
発電だけなら最も高出力な負荷は5Ω程度、発電と使用しない水のエネルギーの相乗平均が最も高くなる負荷は10Ω程度となり、ほぼ両立できる設定であることがわかりました。また相乗平均の最適値で使用していない水の割合は60%であり、当初の目標の40%発電、60%水流温存という環境にやさしい設定に合っていることも検証できました。