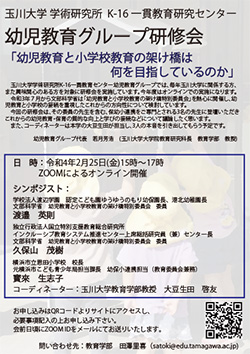玉川大学学術研究所K-16一貫教育研究センター「幼児教育グループ」が、オンライン研修会「幼児教育と小学校教育の架け橋は何を目指しているのか」を開催
2022年2月25日(金)、玉川大学学術研究所K-16一貫教育研究センター「幼児教育グループ」による研修会「幼児教育と小学校教育の架け橋は何を目指しているのか」が開催されました。この研修会は毎年同センターで開催してきましたが、一昨年は新型コロナウイルス感染拡大により中止。今回は教育関係者の熱い期待を受けて、センター関係者の尽力によりオンライン(Zoomウェビナー)での開催までたどり着けました。当日の参加者は幼稚園教諭、小学校教諭、教育行政関係者、大学など教員養成機関の教員など、約300名にのぼりました。
今回のテーマは2021年7月、文部科学省が諮問機関である中央教育審議会(中教審)に設置した「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会(以下、架け橋特別委員会)」を巡り、今後の幼児教育と小学校教育の接続を重視した教育(架け橋プログラム)の方向性について、特別委員会委員を含むパネラーがそれぞれの立場から提言を行いました。
まず、研究会代表である若月芳浩教育研究科長・教育学部教授がシンポジスト(登壇者)の方々のプロフィールを紹介。乳幼児教育・子育て支援の専門家としてメディアでも活躍している大豆生田啓友教育学部教授が当日のコーディネーター役を務めました。
各シンポジストのプロフィールとプレゼンテーション内容は以下の通りです。
シンポジスト プロフィール(敬称略・登壇順)
渡邉英則氏
学校法人渡辺学園 認定こども園ゆうゆうのもり幼保園長、港北幼稚園長
文部科学省 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会 委員
久保山茂樹氏
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 インクルーシブ教育システム推進センター 上席総括研究員(兼)センター長
文部科学省 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会 委員
寳來生志子氏
横浜市立恩田小学校校長、元横浜市こども青少年局担当課長 幼保小連携担当(教育委員会兼務)
プレゼンテーション要旨
1.架け橋特別委員会の概要(渡邉氏)
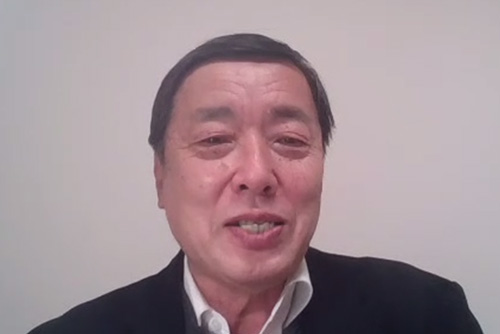
「架け橋特別委員会」委員の一人である渡邉英則氏から委員会の趣旨ならびにどのようなことが議論されているかのお話がありました。まず28人の委員中、現場の幼児教育関係者は4人で、社会福祉、自治体、メディアなどそれ以外の専門家が多いことを紹介。ともすれば「義務教育の前倒し」と見なされることがある幼小接続の議論ですが、議題の中心は「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」であり、幼稚園と小学校低学年の円滑な接続=架け橋となるカリキュラム開発に取り組むことが目的であることを強調されました。その上で「あらためて幼児教育とは何か?が問われている」と指摘。また、幼児教育関係者だけではなく、「幼児教育に関わるすべての人にとっての課題であり、小学校教育以上すべての教育のあり方も問われている」と話し、架け橋特別委員会で「日本の子どもをどう育てるか」という本質的な議論をしていきたいと抱負を語りました。
2.特別支援の視点を含めて(久保山氏)

やはり委員会委員の一人であり、インクルーシブ教育の第一人者である久保山茂樹氏が登壇。久保山氏はまず「つねに幼児教育の現場への憧れをもって現在の仕事に取り組んでいる」と話を始め、特別支援教育の視点から現在とこれからの幼児教育に関する示唆に富むお話を熱く語られました。久保山氏は「特別支援教育と融合したインクルーシブな幼児教育によって保育の質が向上する」と指摘。「……幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、幼児一人一人の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行うようにすること」と記された「幼稚園教育要領」に即した保育を実践する園では、多様な子どもが安心して過ごせる環境と対人関係が構築されていることを、実情に即して解説されました。こうしたインクルーシブな保育の実現のためには、各園と小学校の連携の充実、小学校の保育への理解、さらに地域の教育委員会のリーダーシップが欠かせないことを指摘しました。
3.幼児教育の現場からの視点(渡邉氏)
再び渡邉英則氏が登壇され、3年間にわたる幼小の「架け橋プログラム」で、12のモデル地域における先進事例の開発・実践と、全国的な架け橋期の教育の充実を並行して推進していく中で留意すべき視点を解説。「主体的、対話的で深い学び」「すべての先生が関わるプロセス、組織的な体制づくり」「ICTやオンライン等の活用」に加え、「形式的にならないよう、家庭や地域も一緒に」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を起点とした議論を進めることが大切だと訴えました。また今後小学校に求められることとして「個別最適な学びと協働的な学びの充実」の再確認が大切であると提言。「小学校でも子ども主体の教育に変えていく」必要性を強くアピールされました。
4.小学校の現場からの視点(寳來氏)

現役の小学校校長であり、教育行政で幼保小連携に取り組んだ経験を持つ寳來生志子氏が登壇し、「幼児教育と小学校教育に虹を架けよう」と題したプレゼンテーションを行いました。その要旨は「『考えないスイッチ』が入らないようにする」「子どもたちの興味・関心、わくわく感を大切にする」「子どもにきく」「『手応え』感覚を大切にする」の4点です。寳來氏が校長を務める小学校での取り組みやエピソードを交えて、子どもの立場に立ち、安心や共感にあふれた「子どもが育つ」学校づくりについて解説しました。寳來氏が小学校教育の現場で実感されている「子どもは自ら考える有能な学び手」という言葉がとても印象的で、渡邉氏の主張とも共通する「子どもを育てる」のではなく子どもに合わせた学校づくりという発想の転換が「架け橋プログラム」に必要不可欠であることが改めて認識されました。
 参加者の質問に丁寧に応える
参加者の質問に丁寧に応える(右上 コーディネーター役 大豆生田啓友教授)
3名の方々のお話は幼児教育の質の向上や小学校との接続に関する幅広い領域にわたる、かつ深いお話だったので、オンライン参加されていた方々からは多くの質問と感想が寄せられました。各シンポジストの発言への共感と賛同のほか、「架け橋特別委員会」に関する質問、あるいは未だ意識の高まりが見られない幼児教育、小学校の現場からの切実な声などで、シンポジストの方々が時間いっぱいを使ってモニターの向こう側の参加者に語りかけるように一つひとつに真摯に回答しました。
最後に3人のシンポジストは研修会を振り返って「現場の人が〝子どものために〟力を合わせることが何より大切」(渡邉氏)、「自分自身が架け橋にならねばという思いをあらためて強くした」(久保山氏)、「久保山さんのプレゼンに感動。私も子どもの〝伴奏者〟として頑張っていく」(寳來氏)とそれぞれ決意を述べられました。
インタビュー:研修会を振り返って
K-16一貫教育研究センター「幼児教育グループ」代表 若月芳浩(教育研究科長・教育学部教授)
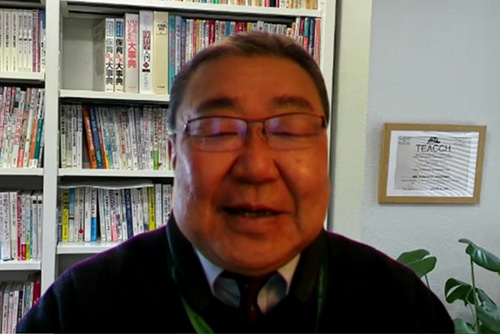
オンライン開催となった今回の研修会は、北海道から沖縄までにいたる地域の多くの方に参加していただきました。あらためて感謝するとともに、幼小の「架け橋」という課題への皆さんの関心の高さが伝わり、大変うれしく思います。 今、広く学校教育で求められている「主体的な学び」は、小学校の段階からではなく、乳幼児期から18歳までの積み重ねであることを今回の研修会シンポジストの方々のお話を通して、深くご理解いただけたのではないかと思います。そのスタート地点である乳幼児期における〝架け橋〟を含めた保育の質の向上が今後ますます求められてくることになります。私たちも、教育・研究を通してその一助となるべく、教育・研究の両面で真摯に取り組んでいきたいと思っています。どうぞご期待ください。