玉川学園造形教育研究会
1961(昭和36)年から1968(昭和43)年までの8年間、美術教育の研究をさらに深め、今後のあり方を探究することを目的に、小学部、中学部、高等部の美術教育の現場において、造形教育研究会が開催された。
1.玉川学園造形教育研究会
美術教育の研究をさらに深め、今後のあり方を探究することを目的に、1961(昭和36)年に第1回の造形教育に関する研究会が開催された。この研究会は、玉川学園小学部、中学部、高等部の美術教育の現場において、大学教員も指導者として参加して行われた。研究会の名称は、第1回は「玉川学園造形教育実技講習会」、第2回以降は「玉川学園造形教育研究会」となった。研究会は毎年行われたが、1966(昭和41)年の第6回より玉川学園教育研究会と同時に開催することとなった。そして、1968(昭和43)年の第8回を最後に、玉川学園造形教育研究会は玉川学園教育研究会に吸収された。
 空き箱を使る工作の授業を見学する参加者(昭和38年)
空き箱を使る工作の授業を見学する参加者(昭和38年)玉川学園造形教育研究会の趣旨について、山田貞実玉川大学教授が『全人教育』第144号(玉川大学出版部発行)に次のように記述している。
従来、一般に開かれている研究会や講習会は講演や討論や見学等に主点がおかれている傾向ですが、美術教育はその性格からしても単なる観念的な理解だけでは実際指導上の力となり難いのですから、実技を通して実際的に具体的に研究しなければなりません。
また、『全人教育』第142号に掲載されている第1回開催の募集案内には、次のように記されている。
美術教育の尊い使命と重要性とが幾多の理論的・実践的研究の累積によって、益々高く認識されるようになりました。
全人教育の旗印のもとに日夜研鑽を重ねています私たちは美術教育のホンモノを究明し、今後の正しいあり方を研究し、一層深めて行きたいと念願しています。
美術教育は単なる観念的な理解だけでは実際指導上の力となり難いのですから、特に基礎教育である小・中学校の美術教育をとりあげて、実技を通して実際に皆様と御一緒に研究したいと思います。
2.第1回の研究会の開催
第1回の研究会は、玉川学園造形教育実技講習会として1961(昭和36)年6月24日から3日間の日程で開催された。北は青森・岩手、南は九州といったように日本全国から約200名の参加者が玉川の丘に集った。小原國芳学長・学園長は、玉川学園メキシコ親善使節団の団長として学生・生徒・児童を連れてメキシコを訪れていて不在だったため、あらかじめ美術教育について録音してあった國芳の話を参加者に聴かせることとした。
 彫塑の技法の実技指導(昭和36年)
彫塑の技法の実技指導(昭和36年)造形教育実技講習会の内容は以下の通りであった。
| 区分 | 内容 | 職名 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日目・24日 | 講演 | 美術教育論(録音) | 学長・学園長 | 小原 國芳 |
| 様式の感覚について | 大学文学部長 | 清水 清 | ||
| 実技指導 | デザイン教育のあり方・紙の彫刻 | 大学教授 | 山田 貞実 | |
| 廃材利用による造形工作法 | 小学部教諭 | 山崎 巌 | ||
| 2日目・25日 | 陶芸の実際(成形の技法) | 大学講師 | 加藤 重右衛門 | |
| 大学助手 | 松田 芳雄 | |||
| 大学助手 | 加藤 正義 | |||
| 彫塑の技法(立体・レリーフの塑造及び石膏型とり) | 中学部教諭 | 佐藤 和男 | ||
| 中学部教諭 | 竹ケ原 慎一郎 | |||
| 染色(捺染法・型紙染) | 高等部教諭 | 五十嵐 良子 | ||
| 中学部教諭 | 山下 いつ子 | |||
| 野外におけるセメント・石材彫刻法 | 小学部教諭 | 内野 清一 | ||
| 3日目・26日 | ヴァイオリンの製作 | 中学部教諭 | 内野 勘一 | |
| 機械による金属加工 | 中学部教諭 | 麻生 増次郎 |
3.第2回以降の研究会
1962(昭和37)年の第2回の研究会は11月19日・20日の2日間で行われた。1日目の午前中は小学部・中学部・高等部の学習参観、午後は小原國芳学長・学園長の「美術教育論」及び山田貞実玉川大学教授の「現代の美術教育は如何にあるべきか」の講演。2日目の午前中は幼稚部、小学部、中学部別の新しい教材技法の研究発表、午後は実技研究。実技研究は、楽器(ヴァイオリンの作り方)、陶芸、染色・織物、木彫と塗装法の4グループに分かれて実施。
1963(昭和38)年の第3回の研究会は11月21日・22日の2日間で行われた。1日目の午前中は学習参観の後、映画「玉川学園の教育」の上映。午後は小原國芳学長・学園長の「全人教育における美術教育」及び清水清玉川大学教授の「造形芸術と創造性」、山田貞実玉川大学教授の「こどもの創造性を高める基礎的教育法について」の講演。2日目の午前中は幼稚部、小学部、中学部、高等部の研究授業、午後は分科会。
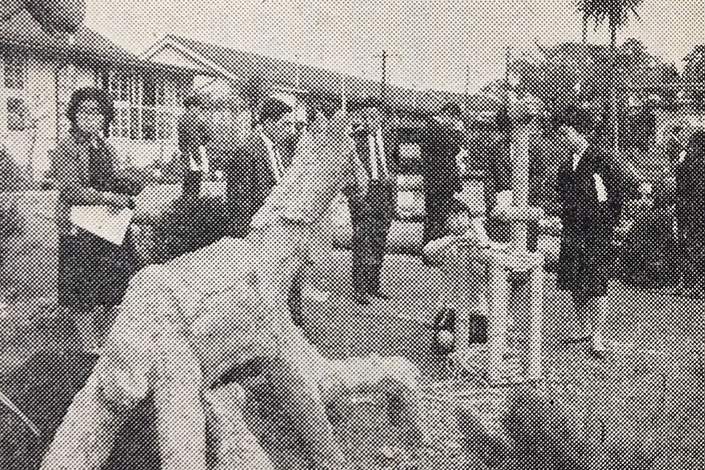 野外彫刻を見学(昭和38年)
野外彫刻を見学(昭和38年)1966(昭和41)年の第6回の研究会から、玉川学園教育研究会と同時開催となった。第6回は11月11日・12日・13日の3日間開催。1日目の午前中は映画「玉川学園の教育」の上映の後、小原國芳学長・学園長の「創造教育論」の講演。午後は全校集会の後、小学部、中学部、高等部の研究発表。2日目の午前中は朝会の後、学習参観、午後は小学部、中学部、高等部別の分科会。3日目は終日実技研修。実技研修の内容は、水墨画、七宝、紙の造形であった。
実技研修をはじめ研究発表、分科会などにおける実技研究は、その時々の教師の専門分野を生かして行われた。中学部を例にとると以下の通りである。
| 回 | 開催年 | 実技研究 |
|---|---|---|
| 1 | 1961(昭和36)年 | 染色、彫塑の技法、ヴァイオリンの製作、機械による金属加工 |
| 2 | 1962(昭和37)年 | 新しい版画の技法、ヴァイオリンの製作、染色・織物、陶芸、木彫と塗装法 |
| 3 | 1963(昭和38)年 | 版画・彫塑、描画、木工、金工 |
| 4 | 1964(昭和39)年 | 中学部における環境美化のためのデザイン教育 |
| 5 | 1965(昭和40)年 | 造形科における立体の指導 |
| 6 | 1966(昭和41)年 | 水墨画、七宝、紙の造形、光の造形、自由なテーマによる造形活動 |
| 7 | 1967(昭和42)年 | 発砲スチロールの彫刻、七宝、リトグラフ(平版)、自由製作の指導とその進め方 |
| 8 | 1968(昭和43)年 | シルクスクリーン、塑造 |
4.玉川教育における芸術教育
玉川教育における芸術教育について、『玉川学園五十年史』に次のような記述がある。
玉川教育における芸術教育は、小原総長の全人教育を通じて全国に喧伝されており、特に昭和三一年からの全国手工芸美術展での数々の受賞が、美術の生活化の成果を示すものとして注目を浴びていたので、この研究会は時機を得たものであった。乏しい材料、設備等の中で美術教育を推進している地方の先生たちにとって、実技の研究会は当を得たものであった。だが、次第にそれらが整備され、また受験教育のひずみの谷間に美術の教科が追いやられると、単なる実技の研究会ではものたりなくなり、やはり、教育の全体像のなかで美術教育はとらえなければならないという考えから、後半、四一年から玉川学園教育研究会と同時に開催することとなり、四四年からは教育研究会に吸収された。
関連リンク
参考文献
- 小原國芳監修『全人教育』 玉川大学出版部
第144号(1961年)、第158号(1962年)、第170号(1963年)、第180号(1964年)、第204号(1966年)、第221号(1968年) - 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』 玉川学園 1980年









