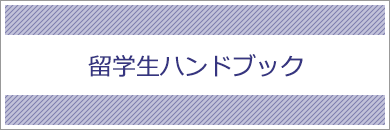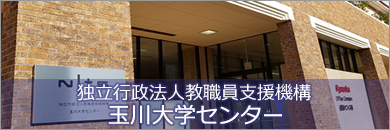研修体験談
ワシントン大学
挑戦することで得た大切な経験と学び
大網 奈子さん
リベラルアーツ学部リベラルアーツ学科
研修参加時の学年:3年
研修タイプ:語学(英語)
研修期間(渡航日含む):2023年7月30日~2023年8月20日 (3週間)

授業では、アメリカでよく使われる英語の文法や言い回しなど、日本の授業で習わない様な英語を学ぶことができ、とても興味深く、英語学習に対する意欲が向上しました。ネイティブ講師の指導のもと学修を進める中で、1週目よりは2週目、3週目と、週を追うごとに先生の話す内容が理解できるようになったことを実感するなど、留学前よりもリスニング力を上げることができました。
週に2回程行われるフィールドワークでは、シアトルの主要な観光地について知ることができました。街の様子や現地の人について知るきっかけとなったたけでなく、ワシントン大学の学生サポーターの方々とも交流でき、授業とは全く違う形で本場の英語に触れられる貴重な機会になりました。また、他国の留学生と授業内でのグループワークや休日の外出などを通して交流することで、英語のスピーキング力を伸ばすことはもちろん、互いの文化について知ることができ、新しい発見が多く溢れ、充実した3週間でした。この研修で出会った友達や先生だけでなく、お店の店員さん等地元の方々と交流することで、日本にいては知ることも無かった文化を感じる貴重な経験を得ることができました。
最初は、自分の英語が通じるか不安に感じていましたが、つたない英語でも現地の人が優しい英語で聞き直してくれ、「下手でも話してみる」ことが大切であると学びました。また、毎日英語に触れ、話す機会があったことで、研修参加前に感じていた「英語を話すことに対する抵抗」が無くなったと感じます。これまでは、アルバイト先に外国のお客様が来店した時、「自分の英語が間違っていたらどうしよう」という不安から接客に抵抗がありましたが、今回の研修を通してその抵抗を無くすことができ、今後は自分から積極的に対応していこうと意識を変化させることができました。
海外研修に参加したことで、英語力の向上だけではなく、知らなかった文化を学び、自分の意識を変えることができました。
ビクトリア大学
自分から挑戦する1ヶ月
戸谷 優花さん
芸術学部アート・デザイン学科
研修時の学年:1年
研修期間(渡航日含む):2025年3月2日~2024年3月30日(4週間)

私は海外に行くこと自体が初めてで、全てが新鮮で様々な新しい体験をすることができました。ビクトリアは、街並みや自然が美しく、人と人の距離が近くとても優しくて、研修を通して訪れなければその良さを知らないままだったと思います。
1日中英語を聞き、話すという環境も初めてで、授業では真剣に先生の英語での指示を聞きとり、クラスメイトと英語で何度も会話したり、簡単なプレゼンテーションに挑戦したりしました。その中で私は文章の組み立てがすぐにできないことや、単語がすぐ思い浮かばないなど、なかなか上手に話せず、自分の課題を見つけることも出来ました。また、日本の春休み期間ということもあり、研修参加者のほとんどが日本人だったため、どうしても日本語を話してしまう場面もあったので、授業以外でも、現地のボランティアの人と話したり、実際のお店で自ら質問してみたりして、積極的に自分から英語を話す機会を作るようにしました。特に、初めてお店での注文やお会計を英語で行ったときはとても緊張しましたが、思い通りに伝わり、店員さんとお話もできたことは、とても嬉しい成功体験となりました。他にも、学校のプログラムで博物館見学やアイスホッケーの試合観戦、バンクーバー旅行にも参加し、個人的にはオーケストラの鑑賞やショッピングなど、日本ではなかなか味わえない体験もすることができました。
この約1ヶ月の研修を終えて、行きの飛行機では全く聞き取れなかった機内アナウンスが、最終的には以前よりも聞き取れるようになったことにとても感動しました。研修校での学びや、新たな出会い、異なる文化の体験などは私にとってかけがえのないものとなりました。この研修で出会った日本人の友達は、研修中でには私の心の支えになり、帰国後も再会のため旅行するほど大切な存在になりました。
やってみたいと思ったら、思った時に動くこと、そして世界は案外近いことを学びました。今後ともこの経験を活かし継続して英語の勉強をし、また世界に飛び立てるように頑張っていきたいです。
リージェンツ大学ロンドン
国境を越えたコミュニケーション
堀口 明音さん
リベラルアーツ学部リベラルアーツ学科
研修時の学年:3年
研修タイプ:語学(英語)
研修期間(渡航日含む):2025年8月9日~2025年8月24日(2週間)

私は今回、平日約3時間の授業に加え、週3回のSightseeingプログラムに参加できるリージェンツ大学ロンドンでの語学研修に参加しました。授業では、ペアワークを中心としたディスカッションが多く、瞬発的に英語を話す力が求められました。初日にクラスへ入ると、日本人は私1人で、さまざまな国の学生が在籍していました。国ごとに英語の発音や話し方が異なり、最初は聞き取りに苦労しました。そして、1週目の終わりに行われたテストでクラス編成が変わり、日本人学生を含む新しい学生も増えました。日本人の学生が増えた後も、私は日本語に頼らず英語で会話することを意識し、これまで話したことのない学生にも積極的に話しかけるよう努めました。その結果、英語を話すことへの抵抗がなくなり、国籍や文化の異なる人々と交流できるようになりました。
Sightseeingプログラムでは、ロンドン市内の自然豊かな場所や美術館、博物館を訪れ、イギリスの文化や歴史に触れる貴重な体験ができました。現地ガイドの英語での説明を理解し、質問をする中で学びを深めるとともに、自らの英語力が実践的なコミュニケーションを通して向上していることを実感しました。
この2週間の研修を通して、私は国境を越えたコミュニケーションに対する自信を得ました。初めての海外留学で不安もありましたが、完璧な英語でなくても、お互いの国を紹介し合ったり、挨拶を交わしたりする中で、言葉や文化の違いを超えて交流できる喜びを感じました。英語が完璧でないことへの不安よりも、伝えようとする姿勢や積極的に話しかける勇気が大切であることを学びました。また、英語を単なる勉強科目ではなく、世界中の人と繋がるための手段として捉えられるようになりました。今後も研修での学びを活かし、さらに英語力を磨き、多様な価値観を理解しながら、異文化の中でも自分らしくコミュニケーションを取る力を高めていきたいです。
アジア・パシフィック大学
多文化社会で学んだ「共に生きる力」―マレーシア研修を通して―
近藤 将太さん
文学部 英語教育学科
研修時の学年:4年
研修タイプ:語学(英語)
研修期間(渡航日含む):2025年8月3日~2025年8月31日(4週間)

私は今年の夏、マレーシアのアジア・パシフィック大学で英語学習や文化交流活動などを通して、多民族国家マレーシアの社会や文化を学ぶことを目的とした短期研修プログラムに参加しました。初めて訪れる国で、英語を使って多様な背景を持つ人々と関わることは大きな挑戦でしたが、それ以上に多くの気づきと学びを得ることができました。現地での生活を通して、街中の看板に複数の言語が併記されていることや、宗教ごとに異なる習慣が尊重されている様子など、多文化共生が日常の中に根付いていることを実感しました。
研修中の経験で特に印象に残っているのは、授業の中で行ったグループディスカッションとプレゼンテーションです。テーマに沿って意見を出し合い、英語で資料を作成し発表するという活動では、マレー系・中国系・ロシア系の学生たちがそれぞれ異なる意見や価値観を率直に述べ合いながらも、互いを尊重して議論を進めていました。その姿勢から、異なる文化や考え方を持つ人々が共に生活するためには、相手の立場を理解しようとする姿勢が欠かせないことを学びました。また、現地の学生たちが流暢に英語を話す様子や、間違いを恐れずに自分の考えを発言する積極的な態度にも刺激を受け、自分の英語力をさらに磨きたいという意欲が高まりました。
この経験を踏まえ、今後はより実践的な英語力を身につけるために、大学内外で行われている英語ディベート会や英語プレゼン大会に参加したり、留学生との交流イベントに積極的に関わったりして、英語を使う機会を増やしていきたいと考えています。同時に、地域の国際交流ボランティアや、多文化共生をテーマとしたワークショップにも参加し、異文化理解を深めながら、マレーシアで学んだ「多様性を受け入れる姿勢」を自分の行動に生かしていきたいです。
将来的には、貿易や物流など国際的な取引を行う企業で、海外の取引先や顧客と英語で交渉や調整を行うような環境で働きたいと考えています。異なる文化や価値観を持つ人々をつなぎ、双方にとって最適な関係を築く「架け橋」のような存在になることが目標です。また、マレーシアでの経験を通して、世界には自分がこれまで知らなかった価値観や考え方が数多く存在することを実感しました。その気づきを大切に、今後は海外のニュースや国際問題にも関心を持ち、さまざまな出来事を多角的に捉えられるよう努めていきたいです。こうした姿勢を通して、柔軟な発想と広い視野を持って行動できる人間へと成長していきたいと考えています。
マレーシアでの研修経験は、語学力の向上にとどまらず、他者を理解し共に成長していく力を養う貴重な機会となりました。この経験を糧に、今後もグローバルな視野を持って学び続けていきたいです。
グリフィス大学
たったの5週間を充実させるために
梅田 萌心さん
リベラルアーツ学部リベラルアーツ学科
研修時の学年:2年
研修タイプ:語学(英語)
研修期間(渡航日含む):2024年1月31日~2024年3月10日(5週間)

私は、幼い頃の海外旅行をきっかけに国際交流に興味を持ち、大学生のうちに海外で生活したいと思い、就活が本格化する前の最後の春休みを活用して5週間のプログラムに参加しました。英語が話せず海外での生活に不安を感じたため親や友人と連絡を取りやすい時差があまりないオーストラリアを選びました。
授業では、事前のクラス分けテストの結果によってクラスが割り振られたため、自分のレベルにあった内容を勉強することが出来ました。また、日本のようにテキストによる演習や単語をただ覚えるのではなく、アニメを教材として利用したり、グループワークやクイズなどを多く取り入れた授業形態であったため印象に残りやすく、クラスの人とも交流を深めることが出来ました。さらに、先生の教え方を観察することで日本との教え方の違いや英語を英語のまま受け入れることの大切さを学び、帰国後の英語学習にも活用することができました。
生活面では、私のホストファミリーはイスラム教徒であった為、イスラム教のルールなど普段は関わることがあまりない文化を体感的に学びました。また、家にいる時は必ずリビングにいるというルールを自分で作り、積極的にホストファミリーと過ごす時間を増やし会話をすることで、最初は会話もままならなかった私の英語力が徐々に上達しました。5週間目には、自分の家族とホストファミリーでビデオ通話をし、簡単な言葉でですが通訳をすることが出来ました。放課後や休日には、ミュージカルやテーマパークなどを観光し、学修と娯楽のメリハリをつけて楽しみつつ、現地の人や物を観察して常に日本との違いについて考えながら文化を学ぶように意識しました。
5週間という短い時間をいかに充実させるかについて考え工夫をすることで、人生の中で一番濃い時間になりました。この経験で得たチャレンジ精神や問題解決力、海外から見た日本の見え方、言語の壁を越えたコミュニケーション力などを今後の就活に活用し、就職後の接客や商品企画など様々な場面で活かしていきたいです。
オックスフォード・インターナショナル・スタディーセンター
「Don‘t be shy!」
松井 鞠さん
農学部生産農学科
研修時の学年:3年
研修タイプ:語学(英語)
研修期間(渡航日含む):2024年2月11日~2024年3月3日(3週間)
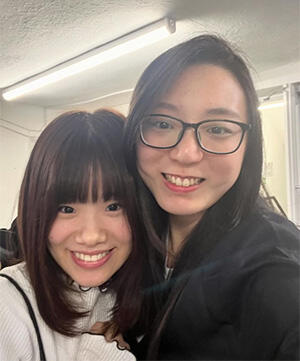
私は、短期間で留学したいと思いSAE研修に参加しました。引率者なしで海外に行くことが初めてで不安に感じることもありましたが、有意義な3週間を過ごせました。
授業では、スペルや発音、文法、単語の意味を主に学び、先生によって授業の雰囲気が変わるため飽きることなく毎日楽しく受講できました。特に発音は口の形や舌の位置、アクセントを丁寧に教えていただき、ネイティブに近い発音を学べて、良い経験ができました。日本では先生が一方的に話す授業スタイルが多く、学生自ら発言する機会が少ないのに対して、研修先では学生が発言を多くできる雰囲気を先生が作ってくださるため、わからないことはその場で聞いて、すぐに解決することができて授業についていくことができました。授業中に先生が何度も「Don‘t be shy.」と声をかけてくれました。積極的に話すことが苦手でしたが、ためらわず自分の意見をしっかりと述べることの大切さを学ぶことができました。休み時間はシンガポールや中国からの留学生と交流する機会が多くありました。授業後は博物館訪問やオックスフォード市内散策などを行うアクティビティの時間があり、展示物や町並みの美しさに圧倒されました。
留学中はホストファミリーにお世話になりました。最初はホストファミリーの話すスピードについていけず戸惑ってしまい、問われたことに答えられずにいると翻訳アプリを用いて話しかけられ、壁を感じたのと同時に悔しい思いをしました。そこで、自分の知っている単語と文法でホストファミリーと会話が続けられるように努力しました。英語を毎日聞くような環境下にいることで耳が慣れ、最終的には翻訳機を使わずに会話ができるようになり、とても嬉しかったです。恐れずにコミュニケーションを楽しむことの大切さを学ぶことができました。
留学中は、英語だけでなく様々な文化に触れることの重要さや楽しさを学ぶことができました。今後は留学で得られた英語スキルを、さらに向上できるように知識を深めていきたいです。
心境の移り変わりと自己成長
正盛 香奈実さん
工学部エンジニアリングデザイン学科
研修参加時の学年:3年
研修タイプ:語学(英語)
研修期間(渡航日含む):2023年8月19日~9月10日(3週間)

1週目は、環境に慣れることに精いっぱいでしたが、オックスフォードの街並みがとてもきれいで、目に入るもの全てを新鮮に感じました。自然公園が多く、公園の木にはリスを多く見かけました。また、主な交通手段であるバスが日本とは異なり2階建てであったことが印象に残っています。英語に関しては、自分の想像以上に聞き取りが難しく、コミュニケーションがうまく取れず悔しい思いをしました。日本と違い、授業中に活発な議論が行われ、ただ講義を聞くだけでなく、先生の発言に対し生徒がその場で質問するような空気に圧倒され、気持ちが焦ってしまいました。先生から「なぜそうなるのか」「どうしてそう考えたのか」等の掘り下げた質問をされた時には、うまく対応できないことが悔しく、少しホームシックになりました。
2週目は、英語の聞き取りに少し慣れ、相手が何を言っているのか分かるようになりました。しかし、時には、聞き取れていなくても、曖昧な相槌などでごまかしてしまうことがありました。また、返答に焦り、文章ではなく単語を並べるだけで話してしまったり、スマホに頼ってしまったりすることもありました。この経験から、焦っていても瞬時に英文を頭の中で考え、口に出せるようになるためには、英文法の勉強と音読等の発話練習が重要であることに気づき、自分の英語力を向上させるための課題を見つけることが出来ました。
3週目は、暑い日が続きましたが、イギリスではクーラーを付ける文化が無いため、窓からか入る風と扇風機の風で過ごしました。学業面では、授業中に自分から質問できるようになり、同じ研修に参加する留学生からその国の挨拶やお礼の言葉を教えてもらった他、おすすめの場所や料理についても会話することが出来ました。最初の週とは違い、自分に自信を持てるようになり、もっとイギリスで過ごして英語を学び続けたいとまで思うようになりました。
研修全体を通して、日本とイギリスの生活スタイルの違いを経験し、自分に自信を持って積極的に行動できるようになったこと、コミュニケーション力が身に付き、冷静に自分の課題を見つける力がついたこと、イギリス英語とアメリカ英語の違いについて、発音や使い方、単語やジャスチャーの意味等をより深く理解できたことなど、とても多くの成果を得ることができました。
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン
悩んでいる時間がもったいない
高橋さん
教育学部
参加時の学年:3年
研修期間:3週間

イギリスへのSAE海外研修は3週間というとても短い期間であり、その間に語学力を大幅に伸ばすことは難しい。では、この3週間をどう過ごせば私にとって最も有意義になるだろうと渡航前の10日間に考えた。
私はイギリスで生まれた。記憶のないうちに帰国したが、イギリスという国や英語という言語は私にとって特別であった。そんな国で私がやったことの一つは利益などを深く考えず、興味に忠実に過ごすことである。自分が生まれた家や当時両親と親しかった近所の方、両親がよく連れて行ってくれていたという地域など、写真でしか見たことないものに触れて自分のルーツを辿ることができた。また、大好きなミュージカル鑑賞に行き、趣味の領域でも充実した日々を過ごすことにつながった。
もちろん、英語に関してもできる限りのことを行った。フロアメイトの韓国出身の女の子や担任の先生との日々の雑談の中で使える相槌を増やせるよう考えたり、その日あったことを英語で日記につけたりするなど主体的に英語を使おうと意識した。その結果、文法的な正誤や語彙力はさておき、会話を続けるスキルが向上したと感じている。帰国後はELFのチューター制度を利用して英語で話す機会を確保するよう心掛けている。
また、様々な知識も吸収するよう努めた。私は実家暮らしで家事を自分中心に行うことがないため、寮で自炊をすることで得た新しい知識も少なくなかった。また、ロンドン大学の講義の中で世界史やマネジメント、多文化共生についてなど、今後の自分のキャリアとつながることを知ることができたと思う。
このように、たった3週間であっても自分がどう考え、過ごすかでその効果は大きく変わる。何のために行くのかではなく行って何をするかを考えると、沢山のイメージが湧いてくるように私は感じた。まずはチャレンジへの決断をすること。そこから道は大きく広がっていくのだと私はこの研修を通して学んだ。
ゲーテ・インスティトゥート(ドレスデン)
研修の意義
土田さん
芸術学部
参加時の学年:3年
研修期間:4週間

研修先のクラスメイトは出身国や年齢だけでなく、それぞれのバックグラウンドも、学校に通う理由も異なるため、そのような環境に自分の身を置けたことはとても貴重な経験となりました。またこの研修は、自分の国を外から見るきっかけにもなりました。クラスメイトの中には日本に来たことがある人や、興味を持ってくれている人もいました。中には日本神話の「国生み」の話を知っている人もいたため、とても驚きました。玉川大学で宗教学などの授業を履修していたため話についていくことができましたが、自国の文化について、今のままでは圧倒的に知識が足りないと痛感しました。
授業では、授業中でもその場で質問できるため、英語ではありましたが、積極的に質問していました。クラスメイトの多くは前日の内容を頭に入れるだけでなく、毎日授業外でもドイツ語を勉強しているため、自分の語学に向き合う姿勢の甘さに情けなくなることもありました。わからない、知らないということが、このようにも悔しく、悲しいことだとは思いませんでした。
午後は授業がないため、その日学習した内容を実践する時間として利用しました。博物館の受付では、ドイツ語ではどのように答えるのかを聞くと、快く教えてくれた人もいました。日本ではあまり意識したことがありませんでしたが、スーパーの表示、街の看板など、日常の生活から様々なドイツ語を学ぶことができました。授業外でもクラスメイトとご飯に行ったり、街を散歩したりしました。一緒に折り紙を折ったり、英語で英語を教えてもらったり、家に招待して頂いたりと、その場でしか経験できないことばかりでした。研修中はあまり実感できていませんでしたが、少しずつでも毎日積み重ねて学習することがいかに大事かを、帰国後時間が経つにつれひしひしと感じています。細々とでも、ドイツ語とそしてこの研修で出会った人たちと今後も繋がることができればと思います。
フレンチ・イン・ノルマンディー
ルーアンで過ごした3週間
片柳 葵さん
芸術学部アート・デザイン学科
研修時の学年:3年
研修タイプ:語学(フランス語)
研修期間(渡航日含む):2024年2月11日~2024年3月3日(3週間)

私は、人生で1番最初に訪れる日本以外の国はフランスがいいと幼いころから思っていました。なぜなら、モン・サン・ミシェルをこの目で絶対に見たかったからです。この研修に参加した理由はいくつかあるのですが、興味を持ったきっかけは、そんな幼い頃からの夢でした。
フランス語がほとんど分からない状態で出発し、はじめは授業を受けてもわからないことばかりでした。常にノートを持ち歩き、わからないことはホストファミリーや研修先のスタッフの方々や現地でできた友人たちに質問し、フランス語を使ってコミュニケーションを取りたいという一心で必死に勉強しました。学んだことをコミュニケーションの中に取り入れ、伝えたいことが通じた時の喜びをはっきりと覚えています。語学を学ぶことの面白さを実感しました。
また、「郷に入っては郷に従え」という言葉の通り、私はホストファミリーと同じような生活をすることを心がけました。フランスで暮らす人々の生活を、身をもって学ぶことができました。研修校は、ルーアンというとても魅力的な街にあり、クロード・モネの連作で有名なルーアン大聖堂やジャンヌ・ダルク教会、大時計などがあります。現地でできた友人とパン屋さんに行ったり、セーヌ川沿いを散歩したり、歴史的建造物を見に行ったり、授業外でも充実した時間を過ごしました。休日には、夢だったモン・サン・ミシェルを見に行くことができ、長年の夢を叶えることができました。この3週間の全てが楽しく、帰りの飛行機では帰国したくないと思ってしまうほどでした。
この研修での最も大きかった成果は、生きる上で何を大切にしたいのかを考えるようになったことです。フランスの人々はそれを明確に持っていると感じることが多く、とても刺激になりました。この3週間での学びは山ほどありますが、その全てが私の今後の生き方を大きく変えるものでした。優しくあたたかな人々と出会い、多くを学び、美しいものを見ることができて幸せな時間でした。
フランスでの挑戦と成果
児玉 悠斗さん
教育学部教育学科
研修参加時の学年:2年
研修タイプ:語学(フランス語)
研修期間(渡航日含む):2023年8月19日~9月10日(3週間)

この研修への参加を希望した理由は、現地の人々と交流し、コミュニケーションを図る中でダイバーシティへの理解を深めたいと考えたからです。また、フランスの文化や生活を理解し、体感することで、自分が想像しているものとどれだけのギャップがあるのかを肌で感じ、学びたいとも考えていました。
研修開始当初は、フランス語がほとんど分からなかったので、言語が話せない、理解できないという不安と恐怖でいっぱいでした。また、自分が今何を考えていてどうしたいのかを思い通りに伝えることができず、とても苦しくもありました。このような状況の中、研修先の先生や事務スタッフの方々が、私の様子を気にかけてくれ、時には、絵や写真を使い、理解できるまで丁寧に教えてくれました。更に、分からないことや、不安に思っていることを伝えると親身になって寄り添ってくれました。その結果、フランス語への不安や恐怖は自然となくなり、自信を持って行動できるようになりました。また、非言語コミュニケーションの大切さを実感しただけでなく、もっとフランスについて知りたいと強く感じました。
私は、将来、教育分野での就職を視野にいれており、教育現場において、今回のフランス語研修での経験や学びを活かし、役立てることができると考えています。例えば、言語をほとんど話すことができない児童生徒に対して、フランスで自分が体験して効果的だと感じた指導方法を実践することで、生徒の不安を少なからず和らげることがでればと考えています。また、海外研修への参加を検討している学生等、新しいことに挑戦する人には、今回の研修での経験をもとに、フランスの人々の温かさ、言葉が流暢に話せなくても伝えたいという気持ちがあれば意思疎通ができること、新しい環境で感じる不安や恐怖は自信に変えることができることを伝えていきたいです。